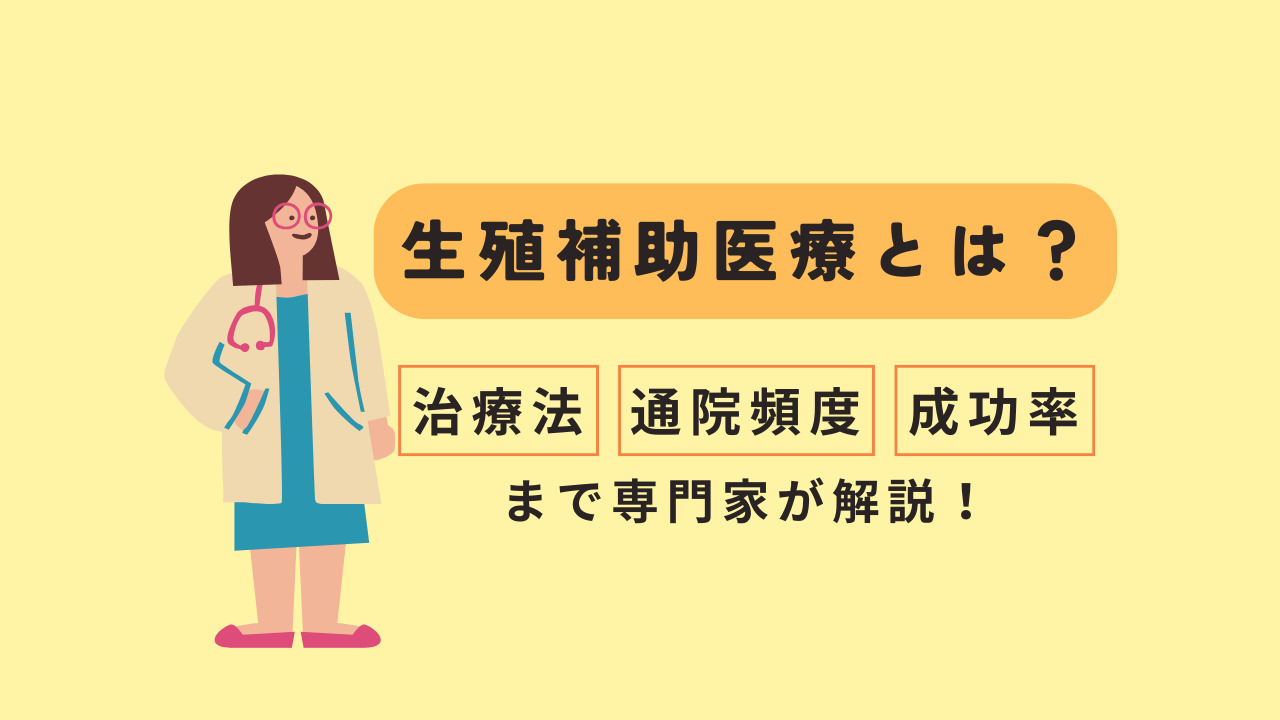「なかなか妊娠できない」「年齢的に焦りを感じている」「友だちからの妊娠報告を心から喜べない」そう思いつつも、不妊治療と聞くと身構えてしまう。
そんなあなたへ、今回は医学的に妊娠をサポートする「生殖補助医療(ART)」についてご説明します。
生殖補助医療とは 1)
生殖補助医療とは、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)と呼ばれる医療行為で、妊娠の確率を上げる治療法です。自然妊娠やタイミング法・人工授精では妊娠が難しい場合に検討されます。
治療の流れは、排卵誘発→採卵→受精→胚移植→妊娠判定という流れが一般的です。特に顕微授精は、精子が少ない・運動率が低い場合でも、治療が行えます。ひとつの精子を直接卵子の中に注入して、授精が期待できる治療法です。
治療への不安(痛み、副作用、通院頻度など)は、事前に専門医や不妊カウンセラー、体外受精コーディネーターなどの説明を受けて納得したうえでスタートすることが大切です。
通院頻度は月経周期ごとに4~10日 2)
生殖補助医療へステップアップをする人は、通院頻度や期間が気になる人も多いでしょう。生殖補助医療では、排卵誘発から採卵、受精、胚移植、妊娠判定までを1周期とします。この1周期にかかる期間は、最短で1~3ヶ月、一般的には6ヶ月ほどです。
一度採卵をして、受精卵をいくつか凍結できる場合もあります。その場合、1周期目で妊娠が難しくても、その後の月経周期で凍結していた受精卵を使用して胚移植→妊娠判定を繰り返すため、妊娠判定までの期間は短くなることが多いです。
不妊治療での通院頻度は女性のほうが男性より多くなります。病院ごとの待ち時間により異なりますが、1回1~3時間程度の受診時間で、月経1周期あたり4~10日の通院が目安です。これに合わせて、採卵の日などは受診に半日以上かかる日もあります。
35歳未満での体外受精成功率は約40~50% 3)
保険が適応されるようになったとは言ってもまだまだ値段は高い、生殖補助医療。治療によりどの程度妊娠を期待できるのかが気になりますよね。
生殖補助医療の成功率は年齢によって異なります。例えば35歳未満での妊娠率は約40~50%ですが、40歳以上では30%前後まで下がる傾向にあります。
また、妊娠をしても妊娠継続に至らない可能性もあります。一般的に流産率は、15~20%ですが、年齢が高くなるほど上がるため、生殖補助医療で出産できる割合は、35歳未満で20%、40歳では10%となります。少しでも早い治療の開始が望ましいでしょう。
まとめ
不妊治療をステップアップして生殖補助医療を受けるとなると、身構える人も多くいるでしょう。不妊治療も年齢が上がると妊娠率や出産率が下がるため、早めの検査と治療がすすめられています。
信頼できる医師や不妊カウンセラーを見つけて、理解と納得をしながら治療を進めましょう。
監修

柴田綾子 先生
淀川キリスト教病院 医長
参考文献
1) 公益社団法人日本産婦人科医会.“11.生殖補助医療(ART)”.公益社団法人日本産婦人科医会.
https://www.jaog.or.jp/lecture/11-%E7%94%9F%E6%AE%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%8C%BB%E7%99%82%EF%BC%88art%EF%BC%89/,(参照2025-06-06)
2) 厚生労働省.“不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック”.厚生労働省.2025.
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30l.pdf,(参照2025-06-06)
3) 登録・調査小委員会.“2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績”. 公益社団法人 日本産科婦人科学会.2024.
https://www.jsog.or.jp/activity/art/2022_JSOG-ART.pdf,(参照2025-06-06)